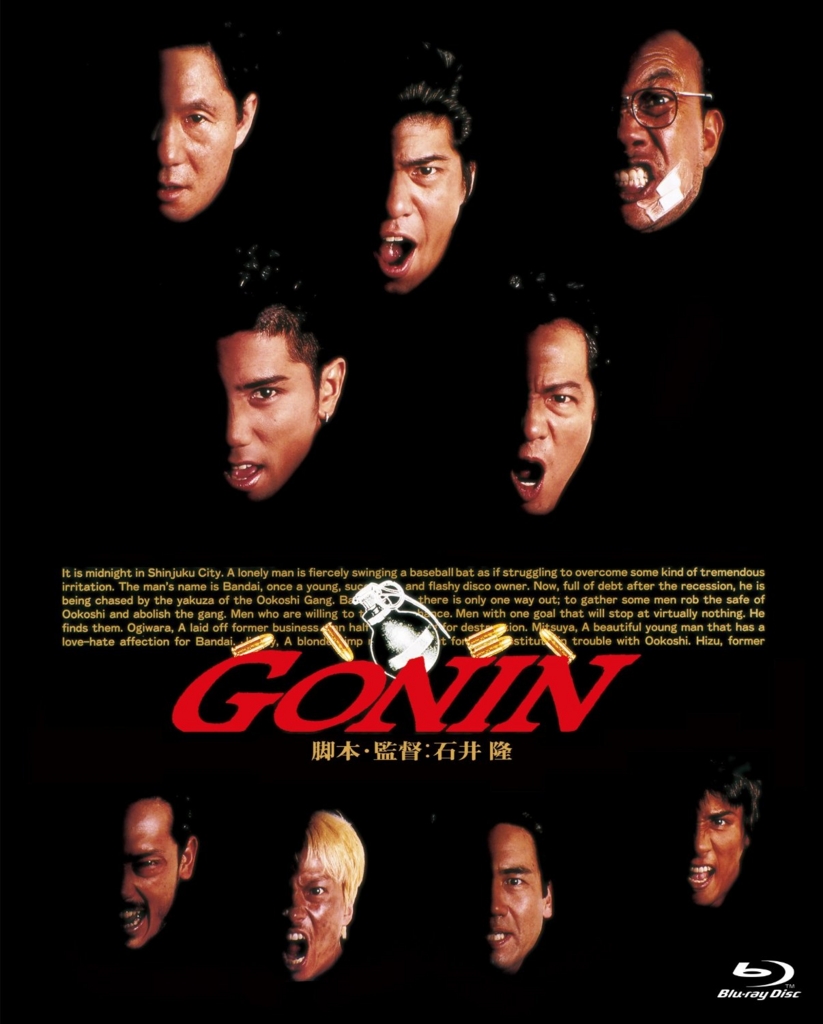会社から帰ってからこんなことは考えたくない。
最近、「表現規制」にまつわるインターネット上の動きでかなり引っかかることがあったので(正直に言えば不満に近い感情だけど、ここではあまり関係ない)考えをまとめるためにこの文章を書くことにした。ちなみにネタバレするとこの文章を書いた結果考えはまとまっていない。
事の発端は人気アニメの性的な2次創作を気に食わない人が、それを、つまり性的なイラストや漫画といった同人的な創作をやめろと提言したことらしい。
インターネットやめろ。
端的に言って、これは「個人的に嫌いな表現を禁止してほしい」というある種の価値観の押し付けであるので、まあバッシングを受けても仕方ないかなと思う。
けれど、筆者が不満を抱いたのはその点ではなくて、上の意見に対するバッシングの在り方と、反論の論理的根拠についてだ。
この種の表現規制に相当する批判が持ち上がったときに必ず湧き上がるのは「嫌なら見るな」と「一度表現規制を認めれば他の表現も危うくなる」という2つの根拠だ。
本当にそれでいいのか?「嫌なら見るな」の一言で事は済まされるのか?それは、そのフレーズに凝り固まった思考停止の一種ではないのか。単純な言い方をすれば、思考がネットに支配されてないか?と、徒然疑問に思ったので色々と考えてた。
詳しくは後述したいのだけど、別に筆者は表現規制に賛成しているわけではない。ただ、上のような言説が氾濫したり、性的2次創作を擁護する人々が数的優位を持って反対意見をぶっ潰してる(ように見える)現状がなんか気に食わない。もっとなんかあるだろ、とそんな気分なだけ、つまり結果どうこう正しさどうこうではなく表現規制に対する言説と運動の在り方について疑念があるだけです。
まあ前置きはいい加減にして、とりあえず「嫌なら見るな」論について批判的に考えていきたい。
強制情報都市
「嫌なら見るな」論の前提には、インターネットはユーザーである自分が情報を取捨選択できるので自分が不快に思う情報をディスプレイ上から切り捨てることは可能である、という論理がある(っぽい)。
嘘じゃん。インターネットでは見たい情報だけをピックアップすることはできない。例えばtwitterやFacebookのタイムラインについて考えてみる。そこにある情報は本当に全てお前が選んだもの?そのプロモーションはもちろん選んでないだろうし、フォローしてるアカウントの投稿がすべてユーザーのニーズを満たしてるわけではない。過度な単純化かもしれないが、ユーザーはフォローしてるアカウントの言説が予測できないからこそフォローしているはずだ。基準となるのは、「この人はこんな情報を提供してくれるだろう」というユーザーの憶測に過ぎない。
また、あるアカウントが提供してくれる情報の種類は多岐に渡るので、競馬の予想情報を提供した後にラーメンの画像をシェアしたり、有名人の訃報や日経平均株価の情報を提供したりするかもしれない。botじゃないんだから当たり前だ。
自分が欲しい情報が得られるなんて保証はどこにもないし、逆のことだって当然ある。好きな小説家をフォローして作家の私生活や新作の概況を知ろうとしたら、見たくもないその作家の日頃の生活の愚痴や奇天烈な政治観の情報が降ってくることだってある。
「それならそのアカウントのフォロー外せ」とご尤もな意見もあるだろうが、先ほど言った通り一つのアカウントから提供される情報は多岐に渡る。「この漫画家つぶやきを見たい!時々不快な情報が混じるけどそれでも有益な情報がある」という場合における選択に正解も不正解もないだろう、それは個人の問題だ。
広大なネット上に氾濫する情報をコントロールすることなんてできない。中国共産党やエルドアンだってできてないんだから、日本の一般人にできるはずがない(極論からのアナロジーは詭弁の一手段です)。
まあSNSなら設定いじくってブロックやミュート設定をいじればある程度はコントロールできるのかもしれない。恐らく、完璧にそれを設定したときあなたのタイムラインは極めて平坦で面白みのないものとなるだろう。
とりあえず、そんな中で、「嫌なら見るな」は無理がある。インターネットやめろ。
派生として「見てもスルーしろ」もあるようだけどこちらも厳しいんじゃないかと。 「不快」の感情は見た瞬間に発生するものだし、そもそもその類の表現が「嫌い」という積極的な感情を持ち合わせている場合スルーすることは難しかったりする。「荒らしはスルー」なんて昔言われたのが懐かしいですね。SNSでの「荒らし」の定義なんて無理じゃね?せいぜいスパムアカウントとクソリプ製造機くらいやろなあ。
問題を一気に難化させてしまうのだけど、「不快なものが目につく」ことが既に問題だったりする。極端に言えば「不快なものが存在し、目につく可能性があること」がそもそもの問題だ。そいつは輪郭を持った存在でないのに敵意を持ってしまうものなんてこの世の中いくらでもある。
結論は最初から出てる。「嫌なら見るな」はあまり意味ないぞ。お前が何かストレス溜まってて何か言った気になりたいなら構わないけど。俺もこの空虚で何もない深夜の天井に得体の知れぬ感情を抱いている。
倒れよ我がベトナム、と国防長官は言った
「ある規制を認めれば別の種類の規制も認めることになる」論について。
これはまあ危惧するべきことなんだろうなあと個人的にも思う。ニーメラーの言葉を引用するのは散々やられているっぽいのでここでは割愛する。
留意するべき点は、こうしたドミノ理論は詭弁や誤謬、もしくは盲信に陥りやすいというところであるし、そうであるからこの言説への批判的視点は怠ってはいけない。冷戦期アメリカ外交を追体験したいならそれでいいと思う。
レベルの問題。また極論だけど、世間一般であまりに少数派かつ非倫理的な表現(具体例なんて出したくないが特定の紛争の難民の少年少女の死体を陵辱したり損壊したりするような表現とか)は、それがいいか悪いかは別として公開を停止させられたりするだろうが、だからと言って別レベルの表現が規制されたりはしないだろう。
自分でも何が言いたいのかこれもうわかんねえな。要は、「これが規制されたらこっちも規制されるぞ!」なんて妄想に囚われずにいること、他の表現との関連について考えることが重要だということにしておく。そうでないと、「これ規制したからこっちも規制ね」と言われたときに「その表現は以前の規制とはここがこうでこうだし関係ないからその規制は不当」とか反論できないし、上述したような極めて公開(範囲は知らん)するのが不適当と思われる表現への歯止めが効かなくなってしまう。
混乱を防ぐためにもう一度例を。「福島県の農産物は放射能の影響で食べると三年以内にガンになると説明する、ちょっと露出の多い衣装を着た女の子のイラスト」(なんじゃそりゃ)を規制する必要があるのはどの点なのか。そんな感じで、いい感じで読み取ってくれ。俺はまだ人類のリテラシーにだって絶望しちゃいない。
当初の問題あんま関係ねえなこれ。まあいいや。

No one hurt
スタンス・スタンス・スタンス
最初にこれ言っておくべきだったと後悔してる。
言いたいことは最初に言っておくべきだ。
問題に対する対処とは主張を徹底させることではなく、対立する複数の主張を調整し妥協点を見つけること、最大公約数の実現。
もちろん、それはイデアであって現実には存在しないかもしれないのだが、インターネットはどうにも妥協させることを知らないらしいし、誰も言ってないらしかったので言っておくことにした。
極めて個人的な思想であるのだけれど、政治とか社会とかいうものは妥協の産物であって、妥協の産物であるべきだと思っている。誰かの主張がそっくりそのまま通るわけがない。あくまで主張とは最大公約を実現するために必要な事前情報でしかなく、そのものを実現させるべきではない。
民主主義だなどと大仰なことは言えないが、少数派の尊重は社会運営の原則だ。自分の考えに反する意見を、自身が多数派であるからとぶっ潰すさまは見ていて気分のいいものではないし、それで最大公約が実現されるとは思わない。
例を挙げる。国民の大多数はそれなりの収入を得て贅沢ではないが貧相でもない生活を送っている。その一方で数パーセントの劣悪な労働環境や低賃金といった労働問題に苦しんでいる人々が存在する場合、この数パーセントの人々に対する救済策の必要性は数的問題ではない。貧困に苦しんでいる人々が多数派か少数派であるかは問題ではないだろ。
(表現規制と労働問題は違うとかそういう批判が予想されるけど、問題解決についての数的優位と必要性の関連性について言いたいんだ。察しろ)
そりゃまあトンデモな少数派だっているだろう。この世は唯一神が拍手するその振動によって成立しているので人類も神のように拍手することで世界の波動と合一し幸福を得ることができると主張する連中のために人類全員が拍手する必要はどこにもない。ただ、そうした集団に出会った際に「貴様たちは間違っている」と言ってぶっ潰す必要もない。彼らがひっそりと奥多摩の山奥のキャンプの中で拍手して神との合一を得られるならそれに越したことはない。一方で彼らが神の波動を使って国民に危害を加えようとする場合、消極的ではあるけれど最大公約の実現としてこれを排除することは問題ないと思う、たぶん。
書いてて思うけどここらへん難しいっすね。最大公約とは誰にとっての最大公約とか基準が曖昧だし、そもそも完全に客観的な基準が設定できない以上やっぱりイデアと言う他ないな。それに表現規制によってある表現を規制した場合最大公約の実現のための情報って言ってるのにそれを自ら規制してメタな矛盾っぽい。33-4。
言いたいことは最後に言うに限る。数的優位と正当性と対策、それぞれの関連性は思ったより高くない。引くことを覚えろ。頼むから一歩引いてくれ。そして、もし問題をある程度、アクチュアリティを持った形で前進させたいのであれば主張を貫徹するのではなく妥協点を探すべきだ。各主張を相対化してください。
このページは書きかけなので加筆・訂正をお願い致します。
じぶんがたり。
「表現」という語は色々厄介な気がする。その語の中には「創作すること」から「公開すること」まで含まれてしまっているからだ。個人的に「創作すること」自体は規制されるべきではないと思う。行為そのものがある種の思想信条を伴っている場合が多々ある(というか全部そうか)ので創作行為の規制は思想の規制と同等になる。書いてて思ったが当然のことをそれっぽく言ってるだけだなこれ。
これも勝手な個人の考えなのだけれど、創作行為はほとんど自分に向けての行為であって極めて私的なものだ。俺は俺が読みたい小説を書いて、俺が見てみたいイラストを描く。他人のために書かれた小説とか不気味じゃないすか。
一方で「公開すること」に関しては規制とかゾーニングが必要だと考えている。特に深い考えがあるわけではなくてネットをだらだら見てて突然エロ画像とかグロ画像見せられるのは嫌だ(この突然が本当に突然だったのかがまた難しいのだけれど)。それはお前の個人的経験と好き嫌いじゃんって言われればそうなのだけれど俺は今個人的経験と好き嫌いの話をしているし表現について個人的経験と好き嫌いに踏み込まず語るヤツがいるんか。さっきお前最大公約がどうとか言ってなかった?
エロ画像を見たいヤツはpixivなりなんなりで探してお気に入りに入れて閲覧してそれでいいじゃないんですか。描くヤツもpixivなり個人サイトで公開すればええやん。pixivの回し者かよ。
人に文句ばっかり言う大人にはなるなよ。